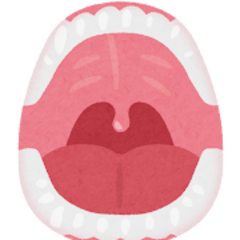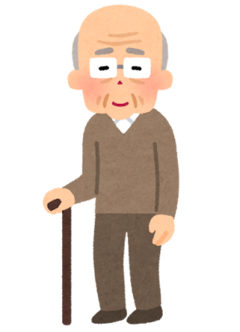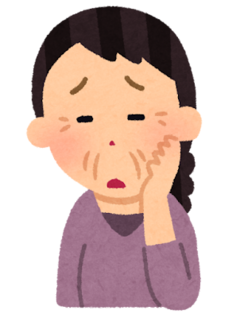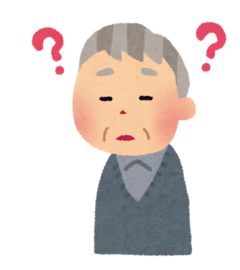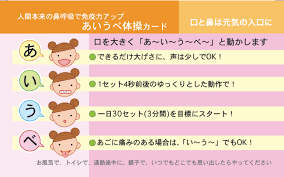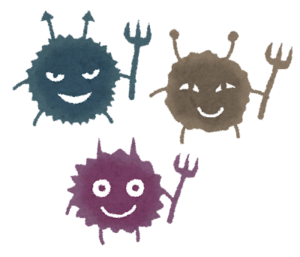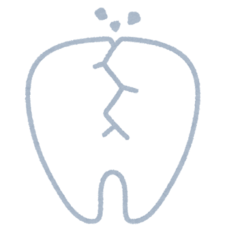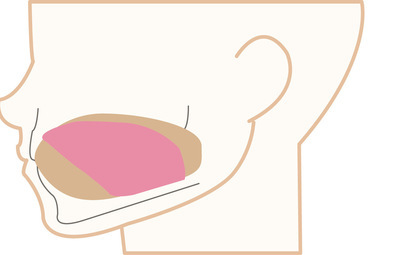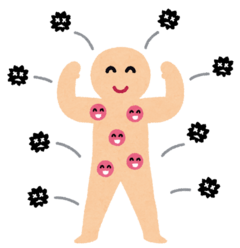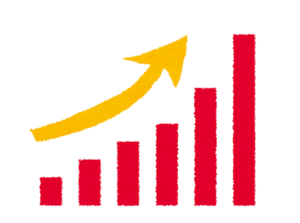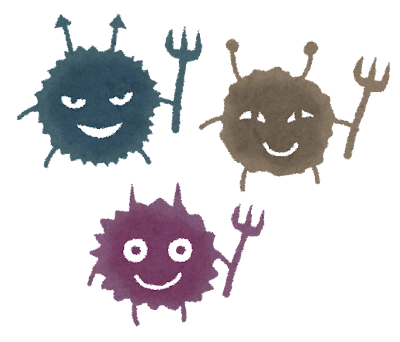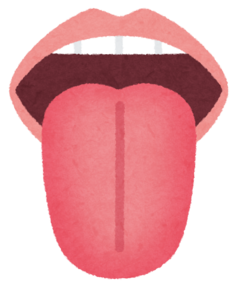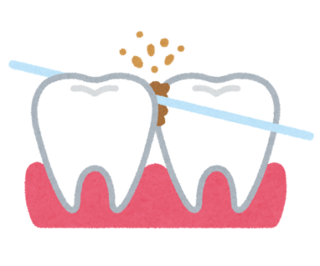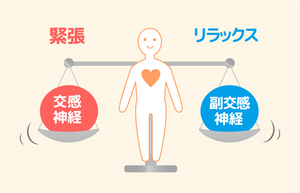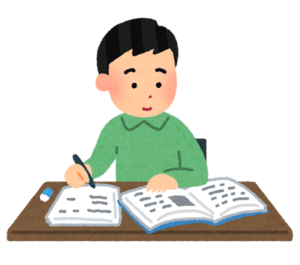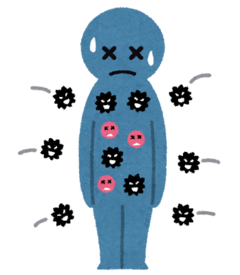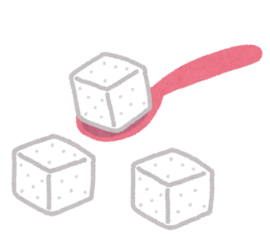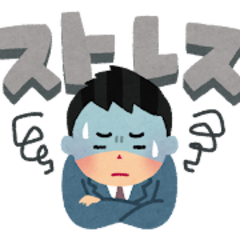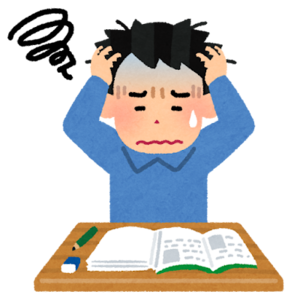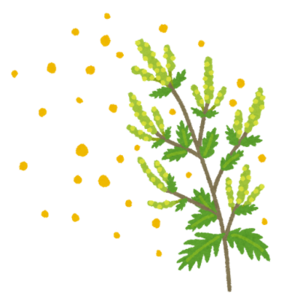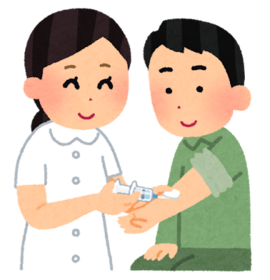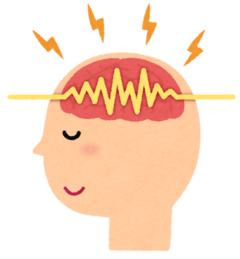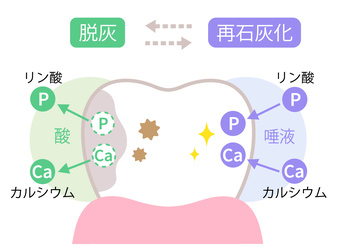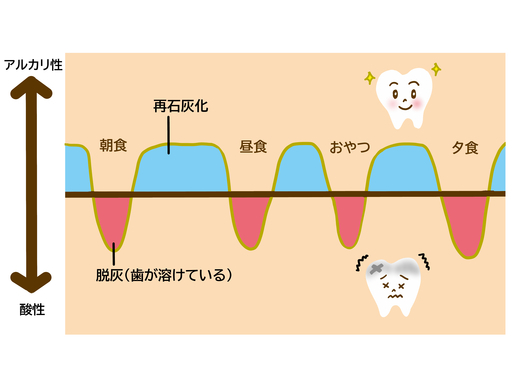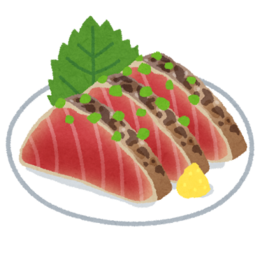フロス?歯間ブラシ?あなたに合うケアグッズの選び方

歯みがきの後に
「フロスや歯間ブラシを使った方がいい」
と聞いたことはありませんか?

私自身、定期検診では
患者さんに毎回のように
お伝えしていることの1つです
ただ、そう言われたものの
「どっちを使えばいいの?」
「そもそも違いってあるの?」
などと迷う方も多いと思います
この記事では
フロスと歯間ブラシの違いを整理し
歯並びや年齢に合わせた
正しい選び方を解説します!
ぜひ、チェックしてみてください!

★「むし歯」について
こちらのブログからチェック
★「歯周病」について
こちらのブログからチェック
【過去の関連記事】
★「歯間ブラシ」について
★「フロス」について
目次
⒈フロスと歯間ブラシの違い
⒉フロスが向いている人
⒊歯間ブラシが向いている人
⒋歯科衛生士が伝える正しい使い方のコツ
⒌まとめ:自分に合うケアで歯周病予防を
⒈フロスと歯間ブラシの違い
フロスと歯間ブラシは
「歯と歯の間を清掃する」
という目的は同じですが
使う目的が異なります
フロスは
歯と歯が接している面の汚れを落とすのもので
歯ブラシだけでは届かない部分の
プラークをしっかり除去できます
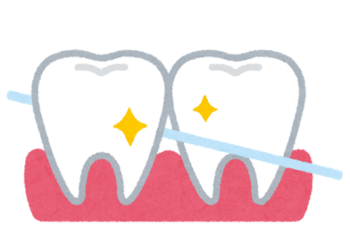
一方、歯間ブラシは
歯ぐきが下がって隙間が広くなった部分や
歯周ポケットの清掃に向いているため
歯周病予防に効果的です
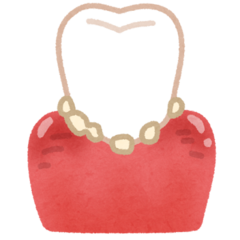
それぞれ目的が違うので
口の状態に合わせた使い分けが大切です
⒉フロスが向いている人
フロスは
歯と歯の隙間が狭い方や若い世代に
主に向いています

歯並びが
密に並んでいる場合は
歯間ブラシが入らないため
フロスが最適です
また、むし歯は
歯と歯の間から発生しやすいため
・詰め物や被せ物が多い方
・むし歯が気になる方
には
積極的に使ってほしいです
初心者には
Y字のホルダー付き

慣れてきたら
糸巻きタイプもオススメです
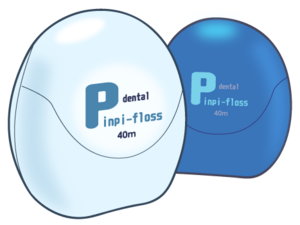
⒊歯間ブラシが向いている人
歯間ブラシは
歯周病がある方や
歯ぐきが下がり隙間が広くなっている方に
主に向いています

若い世代の方でも
歯ブラシで出血しやすい方は
初期の歯周病の可能性が高いので
使用した方が良いです
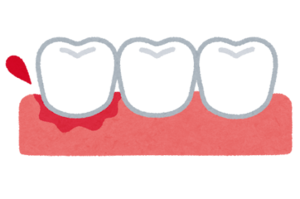
また
ブリッジ・インプラント・矯正装置が
口の中にある方は
歯の根元に
汚れが溜まりやすいため
歯間ブラシを使用することで
効率よく清掃できます
歯間ブラシで
重要なのはサイズ選びです
無理に押し込むと
歯ぐきを傷つけるため
自分に合ったサイズを選ぶことが大切です
★歯間ブラシの使い方は「こちら」をクリック
⒋歯科衛生士が伝える正しい使い方のコツ
結論から言うと
両方使うのが1番オススメです!
たとえば
・朝か昼:手軽にフロスで細かい部分をケア
・夜:歯間ブラシで歯ぐきを重点的にケア
というように
無理なく使い分ければ
歯こうの除去率はかなりアップします!
ブリッジ部分には歯間ブラシ
インプラント周囲にはフロスを入れ込むなど
部位によって
道具を使い分けることもポイントです
清掃道具を使う際の注意点は
・痛みのない範囲でしっかり擦る
・サイズや太さを正しく選ぶ
・歯間ブラシは2〜3週間で交換
これらを守ると
清掃用具の力を最大限に利用できます
間違った使い方は
歯ぐきの傷・出血・炎症の原因になることもあるため
使い始めは
歯科医院での指導を受けると安心ですよ!

当院では、定期検診で
歯間ブラシのサイズのチェックも
させていただいています
⒌まとめ:自分に合うケアで歯周病予防を
フロスも歯間ブラシも
「どちらが正しい」ではなく
「あなたの口に合ったもの」を続けることが大切です
毎日の歯みがきに
フロスや歯間ブラシを取り入れることで
歯周病やむし歯のリスクを
減らすことができます!

ぜひ、自分に合う方法を見つけて
今日から口の健康習慣を始めましょう!
気になることがあれば
ぜひお気軽にご相談くださいね♪

以上です
てらむら歯科では
定期的な検診・クリーニングをお勧めしております
歯の健康=全身の健康です